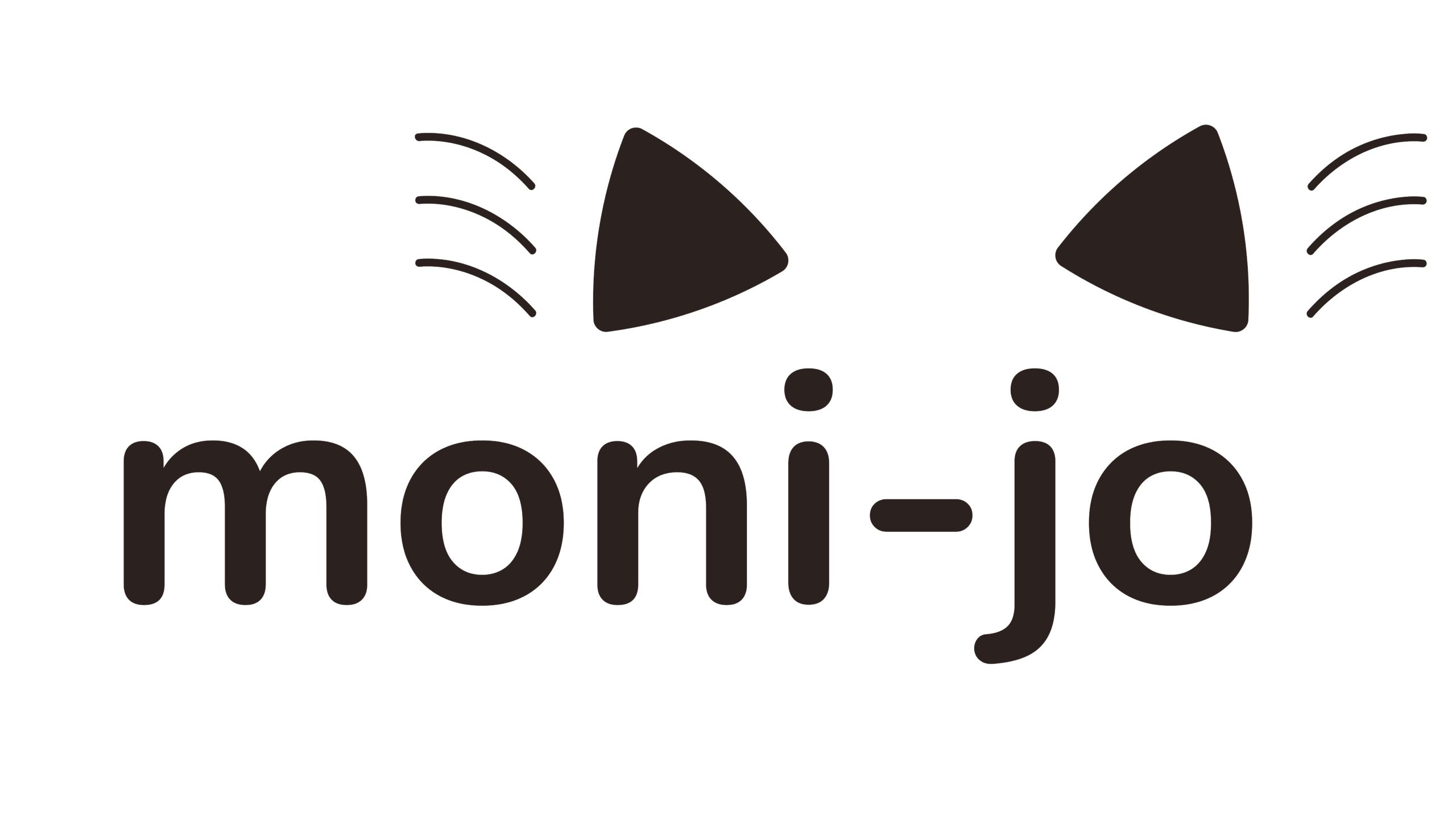ブランド名「moni-jo」の商標登録と、猫耳デザインの意匠権の申請が完了しました✌
2025年7月18日(金)、意匠と商標登録の申請が完了しました。

せっかくなので、自分自身の経験をブログに記載して、今後新製品の開発で知財関係の登録を検討して方々に少しでもお役に立てる事があればと思い、知財関係の申請まで自分が経験した流れをお伝えしたいと思います。
今回の知的財産権の登録・申請について、課題は以下の3つあったと思っております。
①誰に依頼するか?
②どんな知的財産権の申請をするか?
③費用はどうやって捻出するか?
私自身、今回初めて知的財産権に関わった身ではありますので、専門家ほどの知識は有しておりません。
こんな初心者の私でも申請ができたこと、申請で気を付けるべきポイントなどを中心にお伝えしていきますので、細かい部分の誤りがありましたら、ぜひコメントでご教示いただければ幸いでございます。
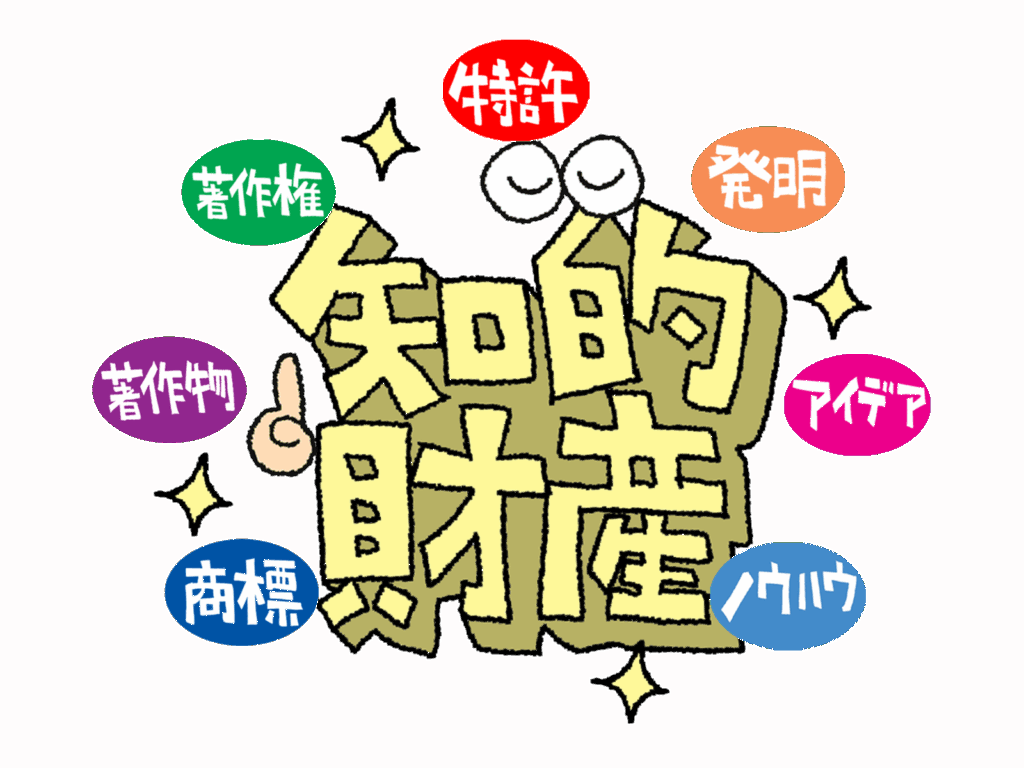
知的財産権には、特許・意匠・商標の3種類がある
今回のmoni-joプロジェクト第1弾の発売に合わせて、特許の申請を最初に考えました。
猫耳という形状は特別なモノではないと考えておりましたので、意匠は必要ないかなと考えておりました。
そして、moni-joというブランド名は大事にしたいと思い、商標登録は必要だと考えておりました。
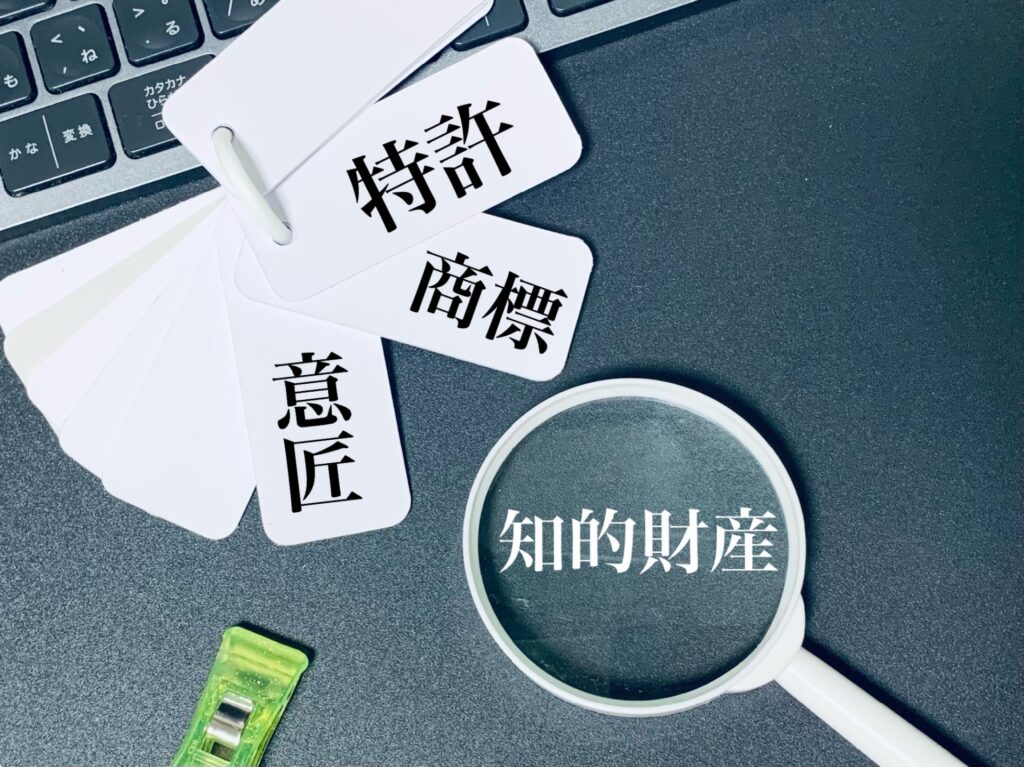
特許とは?
「特許」(Patent)とは、新しい発明をした人に対し、その発明を一定期間、独占的に使用・製造・販売する権利を国が与える制度のことです。
たとえば、新しいエンジン構造や、独自のプログラムアルゴリズムなど、技術的な工夫が対象となります。
これらの「発明」に対して、法律で守られる権利が「特許権」です。
簡単にいうと…
・アイデアを形にした技術の独占権
・他人に真似されないよう保護される
・ビジネス上の優位性を確保できる
特許が保護する「発明」とは?
「発明」と聞くと、飛行機や電球のような大発明をイメージするかもしれませんが、もっと日常的で小さな技術改良も立派な発明です。
ただし、「その新しい技術や解決方法によって得られるメリットがあるもの」が特許取得の有無を左右することになりますので、画期的であっても得られるメリットがなければ、特許の取得は難しいと言われております。
発明の種類
特許取得の発明の種類には、主に以下の様な3つの種類があります。
・物の発明:新しい製品(例:無音キーボード)
・方法の発明:製造方法など(例:省エネのコーヒー焙煎技術)
・物の製造方法の発明:構造+製法の技術(例:AIチップの製造法)
ただし、「アイデアだけ」では特許になりません。再現可能な技術であることが条件です。
特許を取るには?取得の流れと費用
発明したからといって、すぐに特許がもらえるわけではありません。日本では、以下のステップを踏む必要があります。
- 発明の整理と文書化
- 特許庁への出願
- 審査請求(出願後3年以内)
- 審査 → 拒絶理由通知 or 特許査定
- 特許料の納付 → 登録
費用の目安
| 項目 | 費用(概算) |
|---|---|
| 出願料 | 約15,000円 |
| 審査請求料 | 約140,000円 |
| 特許料(3年間) | 年数により異なる(例:初年度2,100円〜) |
| 弁理士費用(依頼時) | 20〜50万円程度 |
自分で書くことも可能ですが、専門的な知識が必要です。
私の場合、勉強のために自分で行うことも考えましたが、こういった法律関係は後々に大きなトラブルになることもあり得ますので、やはり専門家のお力とお知恵をお借りするべきだと思い、弁理士にお願いすることにしました。
特許を取るメリットとは?
✅ 1. 独占的に使える
→自社技術を守り、ライバルに模倣されるのを防げます。
✅ 2. ビジネス価値が上がる
→企業の信用やブランド力が向上し、提携や投資にも有利です。
✅ 3. ライセンス収入を得られる
→他社に技術を使用させ、対価としてライセンス料を得ることも可能。
✅ 4. 防衛手段として使える
→他社からの特許侵害訴訟に対抗する「交渉材料」になります。
登録されるとすぐに出願日からの権利が有効になるため、後から出願された類似技術に優位に立てます。
5. 注意すべき点とデメリット
⚠️ 公開義務がある
出願後、18ヶ月で技術内容が公開されるため、ノウハウの漏洩リスクがあります。
⚠️ 維持コストがかかる
毎年の特許料が必要で、維持にはお金がかかります。
⚠️ 審査に時間がかかる
出願から登録まで、早くても1〜2年かかることが一般的です。
特許と他の知的財産権の違い
| 種類 | 保護対象 | 権利期間 |
|---|---|---|
| 特許権 | 発明(技術) | 出願から最長20年 |
| 実用新案権 | 小発明・改良技術 | 出願から10年 |
| 意匠権 | デザイン・形状 | 登録から20年 |
| 商標権 | ブランド名・ロゴ | 登録後10年(更新可能) |
実用新案という方法もある
「ちょっとした工夫が思いついたけど、特許を取るほどじゃないかも…」
「開発スピードが早い業界で、なるべく早く権利を取りたい」
そんなときに活用できる知的財産制度が「実用新案(じつようしんあん)」です。
どんなものが実用新案の対象になる?
実用新案は「物(モノ)に関する技術」のみが対象で、「方法」や「ソフトウェア単体」などは対象外です。
✅ 登録できるものの例:
・開閉しやすい傘の構造
・取っ手が折りたためる鍋
・配線がしやすいスマホスタンド
・コンパクトに収納できる文具
❌ 登録できないものの例:
・ビジネスモデル
・アプリのアルゴリズムだけ
・製造方法や使用方法そのもの
3. 特許との違いとは?
| 項目 | 実用新案 | 特許 |
|---|---|---|
| 対象 | 物の構造・形状・組合せ | 発明(技術的アイデア) |
| 審査の有無 | なし(登録だけ) | 審査あり(審査請求必要) |
| 登録までのスピード | 早い(数ヶ月) | 遅い(1〜2年) |
| 保護期間 | 出願日から10年 | 出願日から20年 |
| 登録のハードル | 低め | 高い(進歩性が必要) |
ポイント:実用新案は「スピード重視」「コスト重視」で手軽に技術を守る手段!
4. 実用新案登録のメリット
✅ 1. 審査がないので、すぐ登録できる
→特許と違って、審査が不要。出願してから数ヶ月で登録されるので、スピード勝負の業界に向いています。
✅ 2. 費用が安い
→特許に比べて出願料・登録料が安く、スタートアップや中小企業でも導入しやすい。
✅ 3. 他人による模倣を防げる
→登録されると、技術的アイデアを独占的に使用でき、模倣対策になります。
✅ 4. 出願日から権利が発生
→登録されるとすぐに出願日からの権利が有効になるため、後から出願された類似技術に優位に立てます。
意匠とは?
「意匠」(Design)とは、製品などの「見た目のデザイン」に関する創作を指します。
「オシャレなデザインを真似された…」
「せっかく考えた形状がすぐにコピーされる…」
そんなお悩みを持つデザイナーや企業にとって、このデザインに対して独占的に使用できる権利が「意匠権」です。
たとえば、こんなデザインが意匠の対象に:
- スマートフォンの外観(形状・画面配置)
- 家電のデザイン(炊飯器のフォルムなど)
- 椅子・テーブルの脚の形
- 化粧品容器のパッケージデザイン
- UIの画面デザイン(近年はデジタル表示も対象)
2. 意匠と特許・商標との違い
| 種類 | 保護対象 | 保護期間 | 審査内容 |
|---|---|---|---|
| 特許権 | 技術的なアイデア | 出願から20年 | 技術的進歩性など |
| 意匠権 | 物のデザイン・形状 | 登録から20年 | 新規性・創作性など |
| 商標権 | ロゴ・名前・ブランド | 登録後10年(更新可) | 自他識別性など |
ポイント:意匠権は「美しさ」「形状」「デザイン」を守るもの!
意匠の対象になるデザインとは?
意匠法では以下の要素を「意匠の構成要素」として保護対象にしています。
- 形状(モノの立体的な形)
- 模様(装飾パターンなど)
- 色彩(色の組み合わせや配置)
- それらの結合(総合的な見た目)
- 画像(画面デザインやUIも可)
※2020年の法改正で、画面や建築デザインなども意匠の対象に!
意匠権を取得する流れ
意匠登録は、特許庁に出願して審査を経て登録されます。
【取得の流れ】
- デザインの検討と図面・写真の準備
- 特許庁に意匠出願(電子出願が主流)
- 審査 → 登録査定 → 登録料納付
- 登録証の発行 → 保護開始
【登録に必要な書類】
- 願書(出願人情報など)
- 図面 or 写真(6面図が基本:前・後・上・下・左・右)
- 説明書(必要に応じて)
意匠登録にかかる費用
| 費用項目 | 概算(個人出願時) |
|---|---|
| 出願料 | 約16,000円 |
| 登録料(1年分) | 約8,500円(1年ごと更新) |
| 弁理士費用(依頼時) | 10〜30万円程度 |
意匠を登録するメリット
✅ 1. デザインの独占権を得られる
→自分のデザインを20年間、他人に真似されずに使用できます。
✅ 2. ブランド価値・商品価値を高められる
→オリジナリティのあるデザインを法的に守ることで、模倣リスクを減らし、企業や商品の価値が向上します。
✅ 3. ビジネス交渉が有利に進む
→意匠権は資産となるため、ライセンス契約や提携の交渉材料にもなります。
✅ 4. 他社の模倣を差し止め可能
→権利侵害に対して、損害賠償請求や差し止め請求が可能です。
登録する際の注意点
⚠️ 新規性が必要
出願前に公開されたデザインは登録できません。発表・販売前に出願を!
⚠️ 登録前に情報が漏れないように
展示会やウェブ公開で事前にデザインを公表すると、出願が無効になる恐れがあります。
⚠️ 出願時の図面の精度が超重要!
不完全な図面では、意匠の範囲が曖昧になり、模倣品に対抗できないことも。
商標とは?
**商標(Trademark)**とは、商品やサービスに使う「名称」「マーク」「ロゴ」「キャッチコピー」などを他と区別するための“しるし”です。
簡単に言うと「ブランドの目印」。
消費者が商品やサービスを見て、「これはあの会社のものだ」と判断できる役割を果たします。
商標登録することで、**他人が同じ名前やロゴを使うのを法律で禁止できる権利(商標権)**が得られます。
商標の代表例
以下のようなものが商標として登録可能です:
- 商品名・サービス名(例:コカ・コーラ、ユニクロ)
- ロゴマーク(例:NIKEのスウッシュ)
- スローガンやキャッチコピー(例:Just Do It)
- 図形・文字・色彩・音・立体形状など
※近年は「音商標」や「動きのあるロゴ」なども対象に!
商標と他の知的財産との違い
| 区分 | 保護対象 | 主な役割 | 権利期間 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 名前・ロゴ・スローガン | ブランドの識別 | 10年(更新可能) |
| 特許 | 技術や発明 | 技術の保護 | 20年 |
| 意匠 | 製品のデザイン | 見た目の保護 | 20年 |
| 著作権 | 文章・音楽・画像など | 表現の保護 | 創作から70年(原則) |
ポイント:商標は「ブランド名を守る盾」!
商標登録のメリット
✅ ブランド価値を守れる
→他社が同じ名前を使うのを防げます。自社の信頼やイメージを守る効果が大きいです。
✅ 他社とのトラブル防止
→先に商標登録しておけば、名前の使用で訴えられるリスクが減ります。
✅ 権利のビジネス活用が可能
→商標権をライセンス契約して、他社に使わせることも可能です(ロイヤリティ収入)。
✅ 独占使用の強力な武器になる
→商標登録していれば、似た名前・ロゴの使用を法的に差し止めできます。
商標の取得方法
日本では「先願主義」が採用されており、早い者勝ちです。思いついたらすぐ出願を!
【取得のステップ】
- 商標調査(似た商標がすでに登録されていないか確認)
- 特許庁に出願
- 形式審査・実体審査
- 登録査定(問題なければ)
- 登録料の納付 → 登録証発行 → 商標権発生!
商標登録にかかる費用(日本の場合)
| 費用項目 | 概算 |
|---|---|
| 出願料(1区分) | 約12,000円 |
| 登録料(5年) | 約17,200円 |
| 登録料(10年) | 約34,400円 |
| 弁理士への依頼費用 | 5~20万円(難易度や事務所による) |
※自分で出願も可能ですが、拒絶リスクや書式ミスを避けるなら弁理士に相談するのが安全です。
商標登録の注意点
⚠️ 登録できないケースもある
- 単なる一般名詞(例:「リンゴ」で果物を登録)
- 他人と類似している名前やロゴ
- 公序良俗に反する表現 など
⚠️ 使用していないと権利が取り消される
登録後3年以上使っていないと、第三者に「不使用取消審判」を申し立てられ、権利を失うことがあります。
⚠️ クラス(区分)の指定ミスに注意
商品・サービスには「第1類~第45類」までの分類(国際分類)があり、間違えると保護されない場合も。
商標登録が有効なシーン
- ECサイトでブランド販売をしている人
- 飲食店・美容室など、店舗名を長く使いたい事業者
- オリジナルグッズや製品を販売する企業
- YouTubeやSNSで活動するクリエイター
- スタートアップや新サービスの立ち上げ時
依頼先の弁理士の見つけ方
まず、自分自身が苦手で知識の浅いこの知的財産権の部分をサポートしてくれる弁理士を見つける為、いざというときに直接会ってお話できる関係を持っておいた方がよいと思いました。
その為、google検索で「弁理士 東京」というキーワードで検索し、いざという時に会いに行ける距離の弁理士様を探すことにしました。
すると、「弁理士ナビ」というプラットフォームサイトを発見できたので、こちらのサイトから東京都内で近場にある弁理士事務所を探すことにしました。
一度にたくさん問い合わせをすると訳が分からなくなって混乱しますので、まずは3社に絞って問い合わせを行いました。
次に、早急にお話ができる返事の早い弁理士様に絞り込み、早々にウェブMTを行い、その場で実際にお会いできるスケジュールを決め、その2~3日後に事務所へご訪問し、サンプル製品をお披露目しながら説明をし、知的財産権登録について相談を行いました。
この時点で1社に絞り込みました。
そして、いざ登録を行おうと思ったタイミングでこの1社にメールを送ったのですが、2日経っても返事がなく、再送して2日経っても返事がない…。
この時点で1週間を浪費してしまっております。
そして再々送メールを送り、「これは返事が来ないかも…」という焦りから、新たに弁理士を探すことにしました。
改めて「弁理士 東京」で検索をしてみたところ、「比較ビズ」という別のプラットフォームサイトを発見し、こちらで探して観ました。
このサイトのいいところは、条件を入力しておけば、先方からご連絡をいただけるという点にあります。
一旦、ご連絡企業を10社に設定し、この中から3社に絞って連絡をし、最後に1社と契約を行いました。
この比較ビズから弁理士の方々とお話することがセカンドオピニオンの様な状況となり、意匠登録は考えていなかったのですが、皆様のご意見を取り入れて意匠登録をすすめることにしました。
結果的に、不要な費用を削減することにも成功しましたので、はやり複数社とお話をして決定する事の重要さを身を以て知ることとなりました。
補助金や助成金をうまく活用する
各自治体では、新製品の開発や登録を積極的にすすめているところが多く、比較的サポートしてもらいたい補助金/助成金の1つでもあります。
実際、私が今回の件で「費用面でサポートしてもらえる補助金や助成金がないかな…」と探したところ、東京都が行っている助成金事業、中小企業振興公社が行っている助成金事業、そして実際に申請を行った葛飾区主催の新開発事業補助金とありました。
残念ながら東京都主催のものは規模が弊社とは合わず断念し、中小企業振興公社はタイミングが合わず断念、他にどこかないかなと探していたところ、葛飾区主催の補助金があり、タイミングも合ったことから、こちらを活用させていただきました。
申請の結果は早くても半年後…
この知的財産権の中でも意匠・商標申請というものは、すぐに結果の返答が届くものではなく、約半年ほどかかる様です。
その為、現段階では「意匠・商標取得済」とは公表できない為、「意匠・商標申請済」または「意匠・商標出願中」という表現しか使えない状況にあります。
とはいえ、出願したことには変わりはありませんので、提出をした時点で世の中に公表できる様になりました。
しかし、念には念を入れて、プレスリリースするまで公表は控えておきたいと考えております。
(どのみち今発表しても中途半端になりますので…)
まとめ
いかがでしたでしょうか?
私の様な知識ゼロの人間でも、百戦錬磨の弁理士のお力をお借りできれば特許・意匠・商標の登録は可能ですし、費用面で困っている場合は補助金/助成金のサポートを借りて出願することもできます。
せっかくの画期的なアイデアを眠らせておくだけ損しています!
そのアイデアはカタチにしましょう!
こんな私でもできるんですから、知識ゼロでも大丈夫!
ぜひ、同じ開発者・起業家同士として、「ブログ読みましたよ!」という方にお会いできることを楽しみにしております🙌